
スチュワードシップ
活動について
■基本的な考え方
当社は、資産運用会社として、各金融商品の約款等に定める基本方針等に沿って、それぞれの運用目的に沿った運用目標を最大限達成するように努め、受託者責任(忠実義務、善管注意義務)を遂行することを第一義と考えています。
この目的を達成するためには、株式や債券といった投資対象資産の適切な選択だけでなく、それらを発行している企業や団体(以下、「企業等」といいます。)の中長期的価値や持続可能性(サステナビリティ)の向上が不可欠であり、同時に社会の持続可能性の維持が前提となります。
当社は、スチュワードシップ活動を通じ、企業等の中長期的価値や持続可能性の向上に寄与し社会の持続可能性の維持に貢献することで、運用業務における受託者責任を果たすとともに、企業としての社会的責任をも果たしたいと考えています。

■活動の体制
経営と運用の分離の観点から、運用本部内にCIO(Chief Investment Officer)を委員長とし、スチュワードシップ活動に関わる運用本部の関係者で構成する「スチュワードシップ委員会」を設置しています。委員会がスチュワードシップ活動に関する方針を決定し、委員会の統括の下、企業調査アナリスト、ファンドマネージャー、責任投資部スチュワードシップ課が組織的に活動を行います。
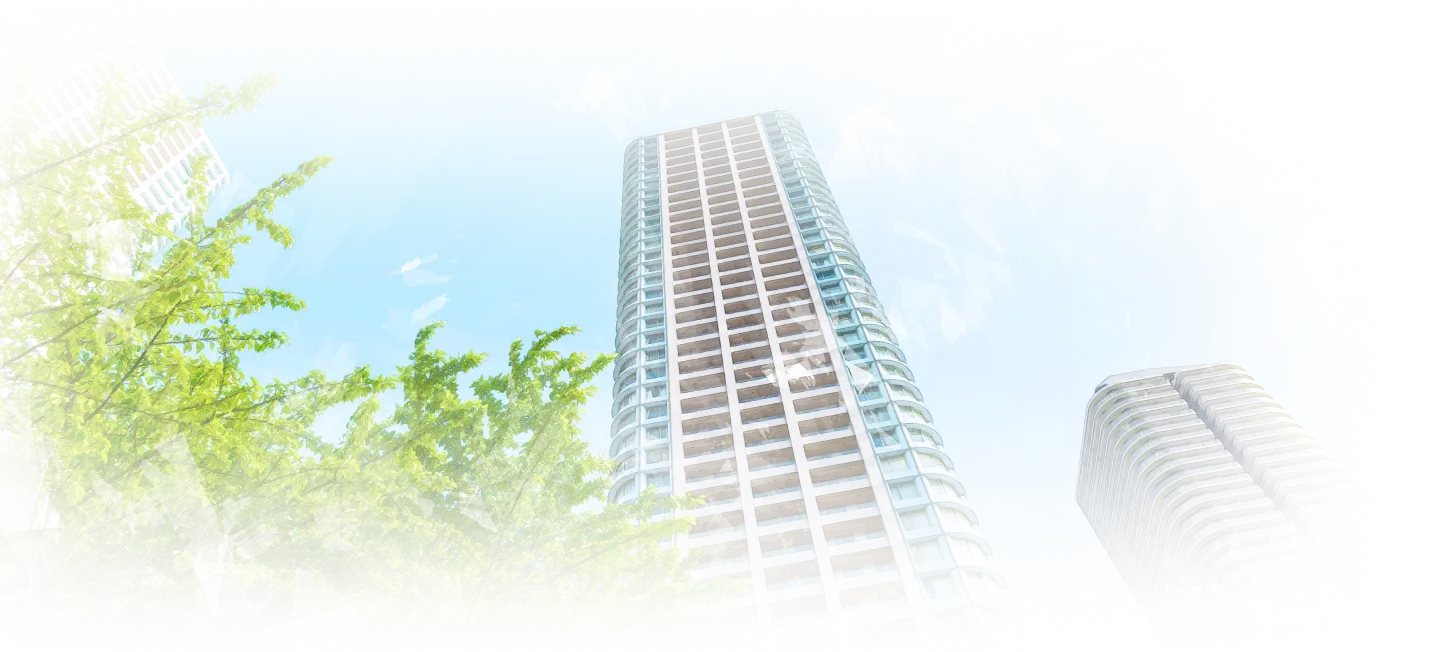
監督委員会は、委員長及び構成員の半数以上を社外取締役とすることで、経営・執行に対して独立性を担保し、牽制機能を果たす体制としています。
活動体制図


活動方針
当社は、スチュワードシップ活動に関する
基本的な考え方に基づき、活動を行います。

ESG
- 当社は、受益者および企業等とともに、インベストメントチェーンの一翼を担うにあたりESGの要素を重視します。
- 当社のESGに対する考え方、重要事項(マテリアリティ)を抽出した「ESG投資方針」を定め、当該方針の下、投資先である企業等や社会の持続可能性の維持、向上に資するべくスチュワードシップ活動を行います。
建設的な対話
(エンゲージメント)
- 建設的な対話では、企業等の状況の的確な把握と認識の共有に努めるとともに、企業等の中長期的価値や持続可能性の向上に資することを目指します。
- 財務面だけではなく、非財務面を含む企業等の状況全般について、企業等と重点的に対話を深めたいと考える観点を整理した「企業等との建設的な対話の方針」を定め、当該方針の下、積極的に対話を行います。
議決権行使
- 議決権の行使に当たっては、企業等の中長期的価値や持続可能性の向上を目的とし、少数株主利益にも配慮します。
- 賛否判断に対する基本的な考え方や具体的な基準を「議決権の行使に関する方針」に定め、当該方針の下、適切に議決権を行使します。


日本版スチュワードシップ・コードの
受け入れについて
当社は、2014年2月に公表された「「責任ある機関投資家」の諸原則《日本版スチュワードシップ・コード》」(以下、「本コード」といいます。)の趣旨に賛同し、2014年5月に、本コードの受け入れを表明いたしました。
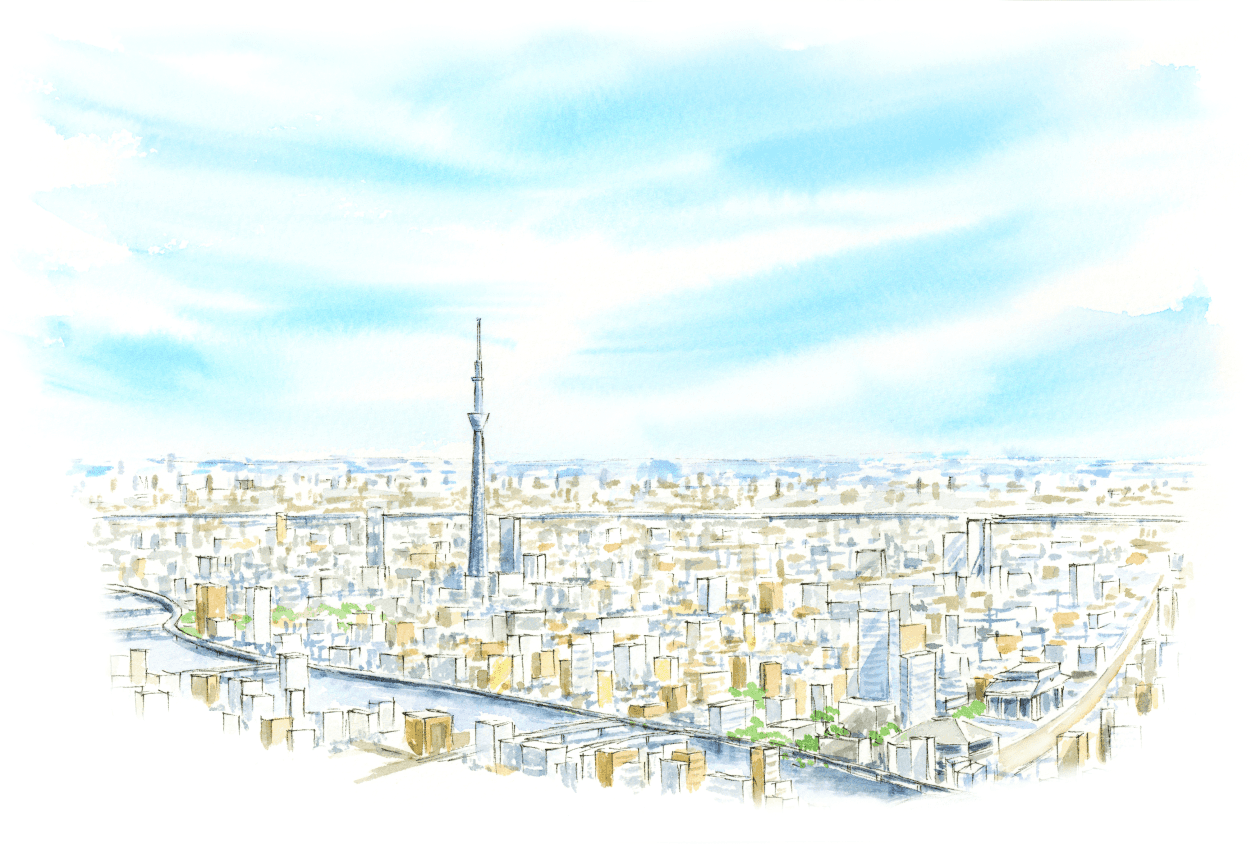
原則1
機関投資家は、スチュワードシップ責任を果たすための明確な方針を策定し、これを公表すべきである。
Read more

原則1
機関投資家は、スチュワードシップ責任を果たすための明確な方針を策定し、これを公表すべきである。

当社は、「スチュワードシップ活動に関する基本方針」を定め、当該基本方針に基づき、各方針を策定し、当社ウェブサイトに公表しています。
・サステナビリティの考慮を含む「ESG投資方針」
・投資先企業との建設的な「目的を持った対話」について定めた「企業等との建設的な対話の方針」
・議決権の行使について定めた「議決権行使に関する方針」
原則2
機関投資家は、スチュワードシップ責任を果たす上で管理すべき利益相反について、明確な方針を策定し、これを公表すべきである。
Read more

原則2
機関投資家は、スチュワードシップ責任を果たす上で管理すべき利益相反について、明確な方針を策定し、これを公表すべきである。

当社は、受託者責任を全うするために、お客様の利益を第一に考えた業務運営に努めるべく「お客様第一の業務運営に関する方針」を定めており、また、お客様の利益が不当に害されることを防止するため、「利益相反管理方針」を策定しています。
スチュワードシップ活動を行うにあたっては、経営と運用の分離の観点から、運用本部内にCIO(Chief Investment Officer)を委員長としスチュワードシップ活動に関わる運用本部の関係者で構成される「スチュワードシップ委員会」を設置し、スチュワードシップ活動に関する方針を決定しています。
また、社外取締役と利益相反管理統括責任者である法務コンプライアンス担当役員で構成される「スチュワードシップ監督委員会」(以下「監督委員会」といいます。)が、スチュワードシップ活動における利益相反管理を監督し、取締役会への報告や必要に応じて利益相反管理に関して改善の勧告等を行う体制としています。
監督委員会は、委員長及び構成員の半数以上を社外取締役とすることで、経営・執行に対して独立性を担保し、牽制機能を果たす体制としています。
なお、議決権行使においては、現在、当社と資本関係を有する企業(大和証券グループ本社等関連会社)や営業上の関係を有する企業(当社投資信託の販売会社およびその親会社)に対する議決権行使を、利益相反が生じ得る特定の場合として管理しています。
原則3
機関投資家は、投資先企業の持続的成長に向けてスチュワードシップ責任を
適切に果たすため、当該企業の状況を的確に把握すべきである。
Read more

原則3
機関投資家は、投資先企業の持続的成長に向けてスチュワードシップ責任を
適切に果たすため、当該企業の状況を的確に把握すべきである。

当社は従来より、企業などに関するリサーチは、資産運用業者にとっての核心的業務のひとつと考え、企業調査アナリストを中心に、社内外の情報網を活用して、情報を常時、幅広く収集し、企業等の状況の的確な把握に努めています。
また、「企業等との建設的な対話の方針」で企業等との対話において重視する項目を定め、企業調査アナリスト、ファンドマネージャー、コーポレート・ガバナンス担当者が、それぞれの立場で企業等との対話を行なっています。対話により得られた知見等を当社内で共有し、企業価値を毀損するおそれのある事項についても早期に把握するよう努めています。
原則4
機関投資家は、投資先企業との建設的な「目的を持った対話」を通じて、
投資先企業と認識の共有を図るとともに、問題の改善に努めるべきである。
Read more

原則4
機関投資家は、投資先企業との建設的な「目的を持った対話」を通じて、
投資先企業と認識の共有を図るとともに、問題の改善に努めるべきである。

当社は、「スチュワードシップ活動に関する基本方針」に基づき、「企業等との建設的な対話の方針」を定めています。
企業調査アナリスト、ファンドマネージャー、コーポレート・ガバナンス担当者は、「企業等との建設的な対話の方針」に基づく対話を行い、企業等の中長期的価値や持続可能性(サステナビリティ)の向上に向け、企業等と認識の共有を図るように努めています。
建設的な対話を行うため、投資先企業から求められた場合には、株式の保有状況を説明します。具体的な対応方法等は、当方針に続く別紙に掲載します。
当社は、アクティブ運用とパッシブ運用に関わらず、当社単独で企業等と対話を行うことを基本としますが、効率的かつ効果的と考えられる場合には他の機関投資家と協働した対話(協働エンゲージメント)を行います。
なお、「企業等との建設的な対話の方針」に基づき、当社は、企業等との対話に際して、当該企業の未公表の重要事実の受領を一切いたしません。
原則5
機関投資家は、議決権の行使と行使結果の公表について明確な方針を持つとともに、議決権行使の方針については、単に形式的な判断基準にとどまるのではなく、投資先企業の持続的成長に資するものとなるよう工夫すべきである。
Read more

原則5
機関投資家は、議決権の行使と行使結果の公表について明確な方針を持つとともに、議決権行使の方針については、単に形式的な判断基準にとどまるのではなく、投資先企業の持続的成長に資するものとなるよう工夫すべきである。

当社は、「スチュワードシップ活動に関する基本方針」に基づき、「議決権の行使に関する方針」を定めています。
当社は、当社の議決権行使に関する予見性を高めること及び、企業等に賛否判断理由を把握していただくことは、企業等との建設的な対話に資するものと考えています。そのため、詳細な賛否判断基準を公開しています。また、必要に応じて企業等との対話を行い、賛否を判断しています。なお、当該賛否判断基準とは異なる賛否判断をした議案や、当該方針において個別判断となる議案については、議決権行使結果を開示する際にそれらの判断理由を示しています。今後も、理由の開示が必要と判断した議案について、わかりやすい開示を行うよう努めます。
利益相反が生じ得る特定の企業についても「議決権の行使に関する方針」に基づいて議決権を行使しますが、
当該方針において個別判断となる議案について、外部の専門機関(グラス・ルイス社)の助言を適用して議決権を行使することで、利益相反の排除と、行使判断の中立性を確保します。
貸株取引に際し、議決権に係る権利確定日をまたぐ場合がありますが、その場合でも、議案の性格に応じ有効な議決権を確保するように管理を行います。
原則6
機関投資家は、議決権の行使も含め、スチュワードシップ責任を
どのように果たしているのかについて、原則として、
顧客・受益者に対して定期的に報告を行うべきである。
Read more

原則6
機関投資家は、議決権の行使も含め、スチュワードシップ責任を
どのように果たしているのかについて、原則として、
顧客・受益者に対して定期的に報告を行うべきである。

当社は、スチュワードシップ活動の主な内容をまとめたレポートを定期的に公表しています。
原則7
機関投資家は、投資先企業の持続的成長に資するよう、投資先企業や
その事業環境等に関する深い理解のほか運用戦略に応じたサステナビリティの考慮に基づき、当該企業との対話やスチュワードシップ活動に伴う
判断を適切に行うための実力を備えるべきである。
Read more

原則7
機関投資家は、投資先企業の持続的成長に資するよう、投資先企業や
その事業環境等に関する深い理解のほか運用戦略に応じたサステナビリティの考慮に基づき、当該企業との対話やスチュワードシップ活動に伴う
判断を適切に行うための実力を備えるべきである。

当社は、経営・執行と運用の分離の観点から、運用本部内に独立した「スチュワードシップ委員会」を設置し、当社のスチュワードシップ活動を統括しています。また、半数以上が社外取締役で構成される「スチュワードシップ監督委員会」が、経営・執行に対して独立性を担保しつつ、スチュワードシップ活動全般に対して牽制機能を果たす体制としています。
スチュワードシップ活動においては、企業調査アナリスト、ファンドマネージャー、コーポレート・ガバナンス担当者がそれぞれの立場で得た、企業等の財務、非財務、持続可能性(サステナビリティ)に関する情報
及び知見を当社内で共有することで、継続的に、対話や判断を適切に行うための実力の向上を図るよう努めています。
また、当社は、当社の行動指針に「持続可能な社会に貢献する」ことを掲げており、社会の持続的成長に資するべく、組織的に取り組んでいきます。
なお、当社は、本コードの実施状況を定期的に自己評価し、その評価内容をレポートにおいて公表しています。

主なイニシアティブへの参画

国連責任投資原則(PRI)は、機関投資家が投資の意思決定プロセスや株式等の保有方針の決定に際してESG課題の視点を組み込み、受益者のために長期的な投資成果を向上させることを目的とする責任投資に関する世界共通のガイドラインです。当社はJapan Advisory Committeのメンバーとして、PRIの日本における活動をサポートしています。

持続可能な社会の形成に向けた金融行動原則(21世紀金融行動原則)は 、国内の金融機関が、 世界の環境・社会問題を解決し、持続可能な社会を形成するために必要な責任と役割を果たすための行動指針として策定されました。
Statement on Fiduciary Duty and Climate Change Disclosure
Statement on Fiduciary Duty and Climate Change Disclosure は、気候変動による企業の業績や投資パフォーマンスへの影響が今後も高まっていくとの認識のもと、企業に対し、年次報告書等の開示書類において、包括的で比較可能な気候変動情報の開示を促すことを目的としています。
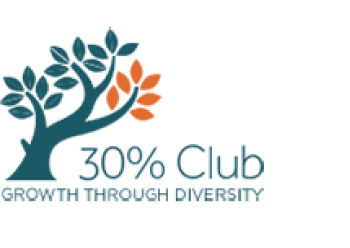
30% Club Japan Investor Groupは、アセットオーナー、アセットマネージャーからなるグループで、投資先企業との建設的な対話等のスチュワードシップ活動を通じて、組織のあらゆる層におけるジェンダー・ダイバーシティとジェンダー平等の重要性を共有することなどを目的としています。エンゲージメントにおけるベストプラクティス策定のワーキンググループに参画しています。

気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)は、2015年に金融安定理事会(FSB)によって設立されたタスクフォースで、低炭素経済への移行過程において、気候変動が財務に与える影響の把握および情報開示を企業に対して求めるものです。当社は2020年12月に支持を表明するとともに、TCFDコンソーシアム(2019年5月に日本で設立)にも参加しています。

ICGN(International Corporate Governance Network)は、1995年に設立された国際的イニシアティブであり、効率的なグローバル市場と持続的な経済の促進に向け、実行的なコーポレート・ガバナンスの構築と投資家のスチュワードシップの醸成をミッションに掲げています。当社はICGN主催のカンファレンス等へ参加しています。

Climate Action 100+は 、2017年に設立された投資家による国際的なエンゲージメントイニシアティブです。GHG排出量の多い大企業に協働エンゲージメント等を通じ、改善を働きかけています。当社は日本の鉄鋼、電機等の企業との協働エンゲージメントへコラボレーション投資家として参加しています。
Investor Agendaは、2018年に設立された機関投資家グループによる活動であり、機関投資家や各国政府が気候変動への取り組みを加速させるための提言を行っています。当社はCOP26開催に向けたグローバル投資家による声明文へ賛同署名を行いました。

Net Zero Asset Managers initiative (NZAMi)
2020年12月に、2050年までに温室効果ガス排出量をネットゼロにすることを目指す世界の運用会社のイニシアティブ「Net Zero Asset Managers initiative (NZAMi)」が発足しました。2024年2月現在、世界で315社以上が参加しており、合計運用資産残高は57兆ドルに達し、多くの日本の資産運用会社も参加しています。当社も2021年12月から賛同し、参加しています。

ジャパン・スチュワードシップ・イニシアティブ(JSI)はスチュワードシップ活動の深化・高度化に資するため、2019年に設立されたイニシアティブです。
Advanceは、2022年12月1日に発足しました。ESG課題のうち、人権問題を中心とした「社会(Social)」の課題をテーマに、協働エンゲージメントを通じて企業の取り組みを促進することを目的として設立された機関投資家のイニシアティブです。人権リスクが高い企業に対し、対話を通じて人権尊重に向けた取り組みを促進しています。
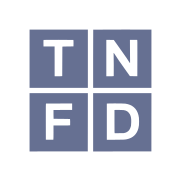
TNFDは、自然関連の財務情報を開示する枠組みの開発・提供を目指す国際イニシアティブです。当社は2023年12月のTNFD立ち上げと同時に、アーリーアダプターとして賛同しました。

