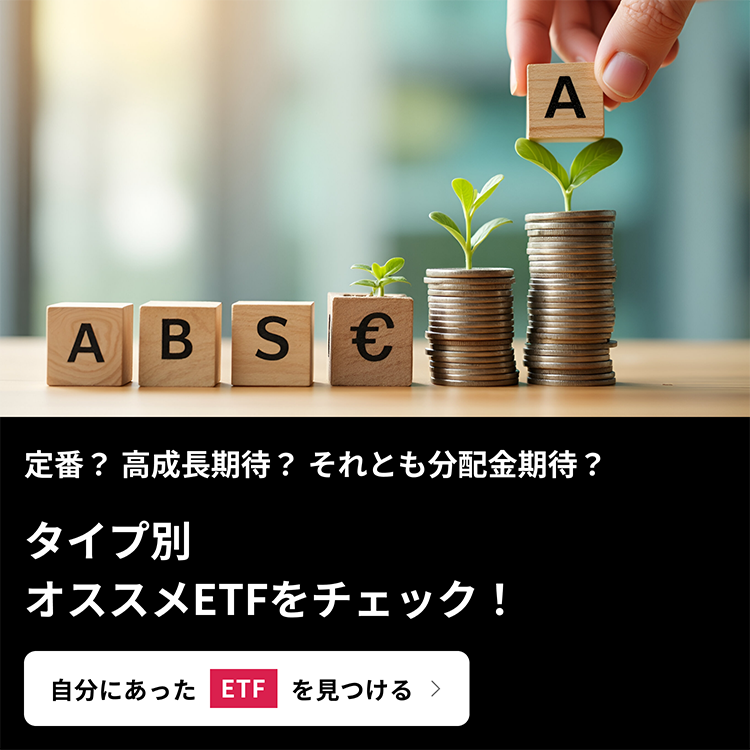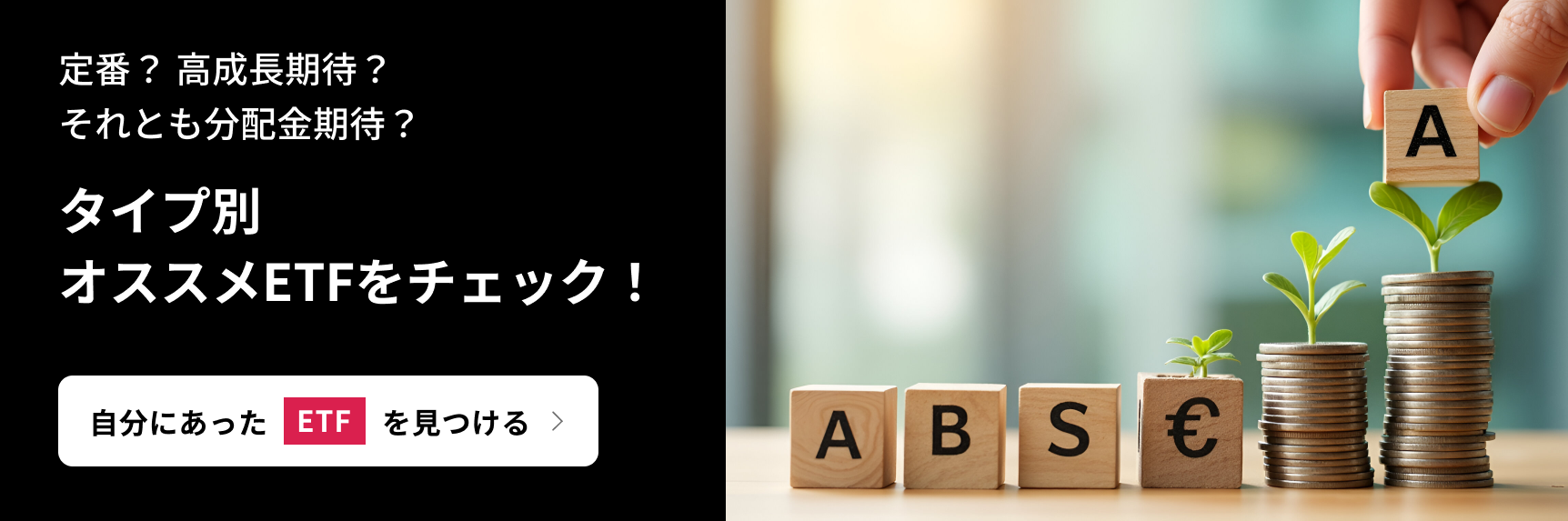退職後の生活をイメージできていますか?
退職すると、現役時代に受け取っていた給与がなくなり、収入は大きく減ることになります。厚生労働省の「令和5年簡易生命表」によると、2024年の日本人の平均寿命は男性が81.09歳、女性が87.14歳です。仮に60歳で退職した場合、退職後には20年以上の時間を過ごすこととなります。
退職後はこれまで貯めてきた金融資産と退職金、そして年金で暮らしていくことになりますが、年金支給年齢は現在の65歳から68歳へ引き上げるという議論もなされており、退職後の長い時間の生活費を、年金のみに頼ることはますます難しくなりそうです。
退職後は日々の生活費に加え、医療や介護など突発的な出費にも備える必要があります。これらの支出を公的年金による収入だけでカバーするのは難しいため、預貯金や有価証券、iDeCo(個人型確定拠出年金)などのこれまでの蓄えに加えて、退職金をいかに活用するかが重要となります。
2019年には「老後2,000万円問題」という言葉が大きな話題になりました。これは金融庁の金融審議会市場ワーキング・グループの報告書における、高齢夫婦の無職世帯は老後の生活費として、30年間で約2,000万円の取り崩しが必要になるという試算に端を発しています。もちろん退職時の金融資産や退職金、年金の受給額は個人差が大きく、「老後2,000万円問題」は誰にでも当てはまるものではありませんが、退職金を含めた退職時の金融資産と、退職後の主な収入となる年金の支給額は、事前に知っておくことが大切です。
老後の生活費の資金源として退職金が重要な理由
老後の生活にとって退職金が重要な理由は、税制面での優遇措置にあります。退職金は長く働いた人に報いるお金ということで、分離課税となっているうえ、ほかの所得にかかる税金と比べて控除額が大きくなっています。
退職金にかかる税金は?
例えば勤続年数20年の場合、退職金が800万円以下であれば、全額非課税となります。800万円を超えた場合には、その超過分に所定の税金がかかる仕組みです。
具体例として、勤続35年、退職金2,000万円の場合、実際に受け取れる退職金の手取り額は以下のようになります(2024年時点の税制に基づきます)。
課税退職所得金額 = (2,000万円 - 1,850万円)× 1/2 = 75万円
所得税・復興特別所得税 = (75万円 × 5% - 0円) × 1.021 = 38,287円
住民税 = 75万円 × 10% = 75,000円
受け取れる退職金 = 2,000万円 - 38,287円 - 75,000円 = 19,886,713円
給与の手取り額と比較すると、退職金の税制が優遇されていることがよくわかります。例えば月収50万円の場合、所得税や住民税、社会保険料など合計で2割ほどの額が給与から引かれて40万円程度しか残りませんが、退職金は上記の例では99%以上が手元に残ることになります。この手取り額の大きさが、老後の生活の資金源として退職金が重要な理由です。
インフレと急な出費に備える必要
退職後は収入が年金などに限られてしまい、公的年金の支給額は決して十分な額とはいえないため、退職金を含む金融資産を切り崩しながら生活することになります。ここで問題となるのがインフレです。2022年頃から世界的に物価上昇が顕著になり、日本でも食料品など生活必需品の値上げが続いています。物価が上がるということは、お金の価値が下がっていくということです。たとえ手元に2,000万円の退職金があったとしても、年平均2%のインフレが続けば、10年後の2,000万円の価値は1,634万円程度まで目減りしてしまいます。
退職後には医療費など大きな出費が急に生じる可能性
退職後は急な出費が発生する可能性があります。その筆頭が医療費です。厚生労働省の推計によると、2019年度の1人当たり医療費の自己負担額の平均値は、65歳以降は年額7~9万円となっており、一見するとそれほど多くないように思えます。しかし、手術が必要になり長期で入院したり、保険適用外となる先進医療を選んだりすれば、自己負担額は跳ね上がることになります。
さらには介護が必要になれば、介護費用がかかります。長く生きることになれば、自宅の修繕も必要になるかもしれません。お子さまの世話にならず老後を過ごしたいという方は、老人ホームなどの施設への入居も選択肢になるでしょう。しかし、今後もインフレが続くことになれば、退職金を預貯金のままで置いておくとお金はどんどん目減りして、こうした大きな出費に備えることが難しくなります。
インフレに負けない退職金の活用法
したがって、お金の寿命を延ばすためには、退職金を金融商品で運用することが重要となります。現役世代の資産運用は「長期的に大きく増やすこと」が主眼となりますが、退職後の資産運用は「お金が減るスピードを遅らせる」という観点が重要です。
ただし、退職金全額を投資するのはリスクが大きいため、「出費に備えるお金」は安全性が高く換金しやすい運用を行い、「すぐに使わないお金」は投資に回すなど、適材適所の運用も求められます。
大きな出費に備えるお金は、元本割れしない安定運用
自宅の修繕、介護費用、有料老人ホームや介護施設への入居など退職後に必要となる出費のうち、金額が大きいものについては、定期預金のような、基本的に元本割れを回避する運用が適しています。
すぐに使わないお金は、資金の寿命を延ばす運用を検討する
大きな出費に備える分以外のお金は、将来的には生活費として取り崩していくことになりますが、退職直後は「すぐに使わないお金」と位置付けることができます。退職金を含む手持ちのお金のうち、すぐに使わないお金については、短期的にはある程度の値下がりを許容しつつも、先々の値上がりが期待できるリスク資産に投資することにより、資金の寿命を延ばすことを検討するといいでしょう。
手始めに、退職時の金融資産を元手にして取り崩す期間を定めた場合に、運用利回り別に毎月いくら取り崩せるかを確認してみましょう。
取り崩す期間が25年間の場合、毎月取り崩せる金額の目安
| 利回り/金融資産額 | 1,000万円 | 1,500万円 | 2,000万円 | 3,000万円 |
|---|---|---|---|---|
| 0.1% | 33,000円 | 50,000円 | 67,000円 | 101,000円 |
| 1% | 37,000円 | 56,000円 | 75,000円 | 113,000円 |
| 3% | 47,000円 | 71,000円 | 94,000円 | 142,000円 |
| 5% | 58,000円 | 87,000円 | 116,000円 | 175,000円 |
例えば運用に回せる金融資産が1,500万円ある場合、年利0.1%の定期預金では毎月5万円しか取り崩せませんが、リスク資産に投資することで年利3%の運用ができれば、取り崩せる金額は毎月7万1,000円にまで増やすことができます。
そして下記の表は、60歳から毎月10万円ずつ取り崩す場合に、運用利回りが高くなるとお金の寿命がどれだけ伸びるかを示したものです。
60歳から毎月10万円ずつ取り崩す場合の資産の寿命の目安
| 利回り/金融資産額 | 1,000万円 | 1,500万円 | 2,000万円 | 3,000万円 |
|---|---|---|---|---|
| 0.1% | 68歳5カ月 | 72歳7カ月 | 76歳10カ月 | 85歳4カ月 |
| 1% | 68歳9カ月 | 73歳5カ月 | 78歳3カ月 | 88歳10カ月 |
| 3% | 69歳8カ月 | 75歳9カ月 | 83歳2カ月 | 106歳4カ月 |
| 5% | 70歳10カ月 | 79歳8カ月 | 95歳11カ月 | - |
定期預金での運用では、3,000万円あっても85歳で底を突いてしまいます。一方、年利3%の運用ができれば100歳を超えても資金は尽きないため、毎月の取り崩し額を増やすことも検討できます。
ただし、退職後の10年、20年でインフレがさらに進むことが考えられます。物価が上がればお金の実質的な価値は目減りするため、取り崩せる金額はより少なく、資産の寿命はより短く見積もっておいた方が安全です。
「資金の寿命を延ばす運用」にNISAの非課税メリットを活用
運用益が非課税となるNISAのメリットを活用することで、資金の寿命がさらに延びることが期待できます。課税口座(特定口座・一般口座)では現在、売却益や分配金による利益には約20%の税金がかかりますが、NISA口座では非課税となり、利益を全額受け取ることができます。
NISAの成長投資枠は、非課税投資枠の上限が年間240万円で、総額1,200万円です。投資が可能な全額を1年間で一括投資するには足りないですが、例えば課税口座(特定口座・一般口座)を併用したり、金融商品を購入するタイミングを数年間に分散したりすることで、NISAを最大限活用できるようにすると良いでしょう。
退職金運用のポイントと注意点
退職金運用で注意すべきことは、大きく減らすリスクを避けることです。退職金は取り崩しながらの運用となるため、ひとたび価格が暴落して元本が大きく減ってしまうと、そこから挽回するのが難しくなってしまうからです。株式の比率を高くし過ぎないなど、現役世代がお金を増やすための資産運用とは異なるアプローチが求められます。そして、急な出費が発生したときに備えて、換金しやすい商品を選ぶことが大切です。
また、取り崩しながらの運用においては、利益の一部が払い出される分配金を有効活用できます。高配当株式やREIT(不動産投資信託)を投資対象とする、高い分配金が期待できる金融商品が有力な選択肢になります。
以上のことから、退職金運用では以下の点に注意するといいでしょう。
- 一括購入を避け、購入時期を分けることで高値づかみを防ぐ
- 株式など値動きが大きい金融商品への集中投資を避け、債券やREITなども含めた分散投資をする
- 価格変動が大きい商品や透明性が低い商品、すぐに換金できない商品を避ける
- 高い分配金が期待できる商品を活用する
年齢とともにリスクを下げて、より「減らさない運用」を心がける
退職金運用は、年齢が進むにつれて、より「減らさない運用」へとシフトしていくことが大切です。退職直後は、お金が必要となる時期がしばらく先となるため、増やすことを主眼に置いて株式やREITの割合をやや高めにして、運用利回りの向上を狙うと良いでしょう。そして年齢が進むにつれて株式の割合を低くして債券の割合を高めるなど、リスクを軽減したポートフォリオにしていくと安心です。
NISAで退職金を運用するならETFが有力な選択肢に
「減らさない運用」で重要なのは、株式や債券、REITなど幅広い資産への分散投資です。分散投資がしやすく、透明性が高いうえ換金しやすいリスク資産には、投資信託やETFがあります。特にETFは運用中のコストである信託報酬が比較的低いというメリットがあるため、退職後の20~30年にわたる長期運用に適しているといえます。
国内株式に投資するETFの例
海外株式に投資するETFの例
海外債券に投資するETFの例
REITに投資するETFの例
老後資金の準備は退職前から
少子高齢化の影響で公的年金の受給額が今後も減ることが予測されているうえ、退職金の支給額も減少傾向にあり、さらにはインフレが進むことを想定するのであれば、老後資金を増やすための自助努力がますます重要になります。
現役世代の方は退職後に備えて、NISAやiDeCo(個人型確定拠出年金)といった非課税制度を早いうちから活用して、余裕資金を投資に回すことを検討しましょう。
まとめ
退職後は年金が主な収入源となり、多くの方は年金だけで生活することが難しいため、貯蓄などの金融資産を切り崩しながら生活することになります。その中でも退職金は税制優遇があるため手取り額が大きく、退職後の生活費の原資として大きな役割を果たします。
退職金は「出費に備えるお金」として一部を預貯金などで保有しておき、残りはリスク資産で運用して、資産の寿命を延ばすことを目指します。実際に毎月いくら取り崩せるか、あるいは毎月決まった金額を取り崩すと何歳で資金が尽きるかなど、例えば下記ページの「取り崩しシミュレーション」などで確認しておくといいでしょう。
運用利回りが高いほど資産の寿命は延び、取り崩せる金額は増えますが、退職金運用では「大きく減らさないこと」が重要であり、リスクを抑えた運用が求められます。基本は株式や債券、REITなど複数の資産に分散投資すること。その際にはNISAで非課税メリットを享受できるうえ、運用時の手数料が比較的低いETFも選択肢の1つになるでしょう。