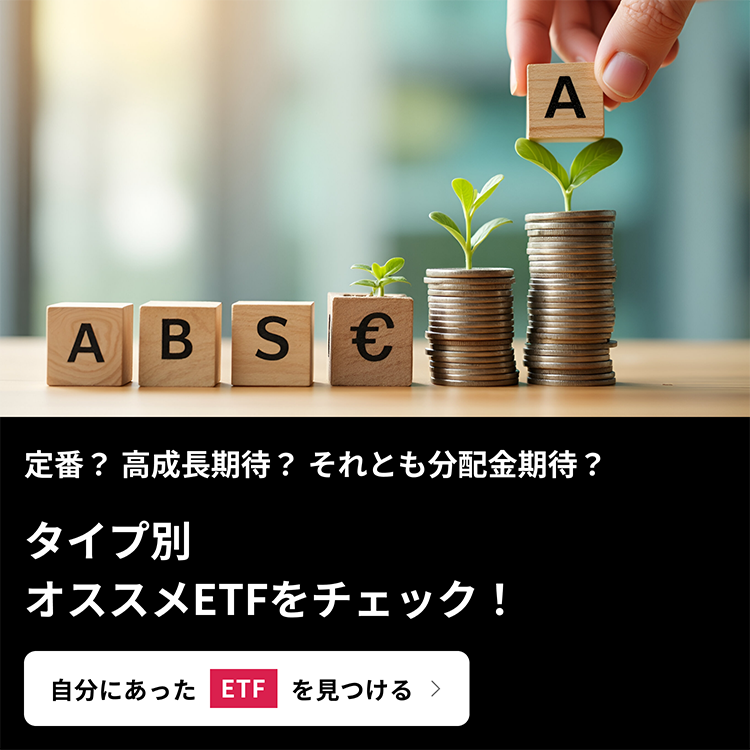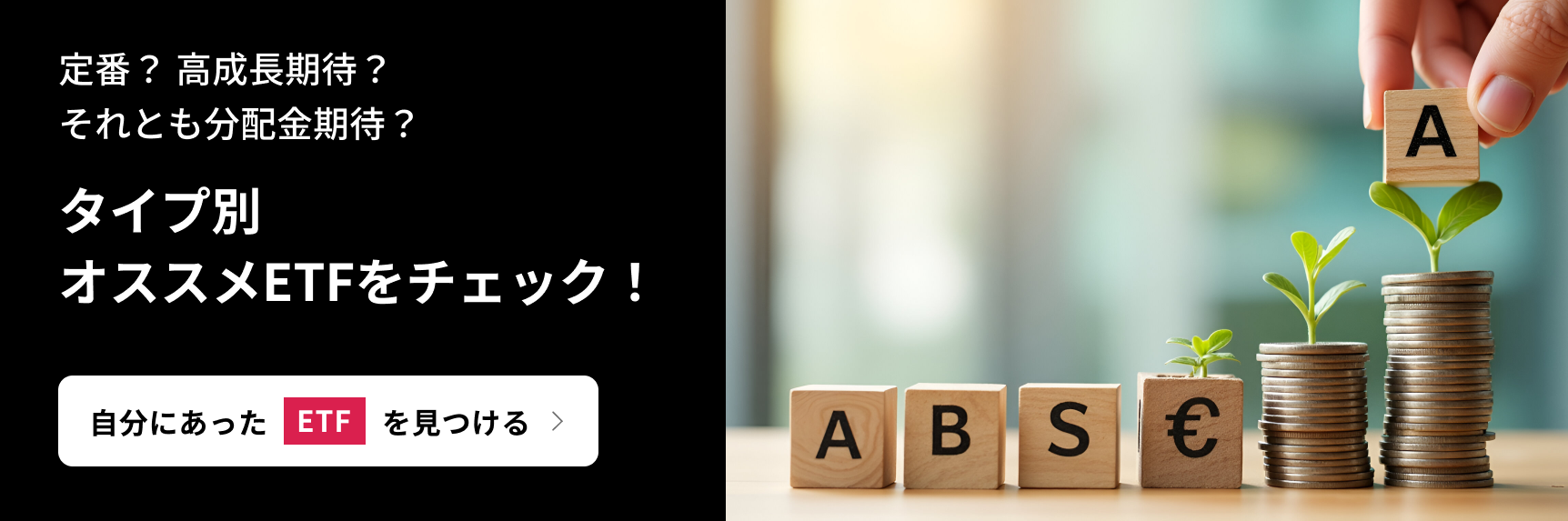高配当株とは?
国内株式の個別銘柄への投資で得られる利益には、値上がり益と配当、そして株主優待の3種類があります。1株当たりの年間の配当金額の合計を現在の株価で割ったものを「配当利回り」と言いますが、この配当利回りが相対的に高い株式のことを「高配当株」と呼びます。
近年は、東京証券取引所(東証)による「資本コストや株価を意識した経営」の要請を受け、日本企業が株主還元に積極的に取り組むようになりました。例えば自社株買いや株主優待、そして配当の支払いです。東証による要請の影響もあって配当は株式市場全体で増加傾向にあり、高配当株投資への注目はさらに高まっていくと考えられます。
高配当株には厳密な定義はありませんが、配当利回りが3%以上、もしくは4%以上の銘柄を指すことが多いようです。2025年3月時点のプライム市場の単純平均利回りは2.31%でした。
国内株式の市場別・株価指数別単純平均利回り(2025年3月)
| プライム市場 | 2.31% |
|---|---|
| スタンダード市場 | 2.44% |
| グロース市場 | 0.74% |
高配当株に投資するメリット
日本は長いゼロ金利時代を経て「金利のある世界」になったとはいえ、預金金利はまだまだ低く、2025年4月時点では2年物の定期預金の金利がようやく0.3%を超えてきた程度です。さらに足元では原材料価格の高騰などによりインフレが進行しており、預金金利の上昇をインフレ率が上回っている状況です。
預金の利息だけでお金を大きく増やすことは現実的とはいえません。現在の生活水準を維持し、退職後に備えるためには、投資による資産運用が重要です。一般的な預金より利回りが高く、比較的安定した配当収入が期待できるメリットがある高配当株は、その有力な手段の1つといえるでしょう。
保有する株式を売却しなければ利益が確定しない値上がり益と違って、配当は株式を売る手間をかけることなく、定期的な収益が期待できます。
高配当株の注意点
とはいえ、配当利回りが高いからといって必ずしも高い収益が期待できるとは限りません。配当利回りがなぜ高くなっているのか、その背景を知ることが大切です。
配当利回りは「年間の配当÷現在の株価」という割り算で求められます。分子に当たる配当が増えれば配当利回りは高まりますが、分母となる「現在の株価」が下がっても配当利回りは高まります。経営に対する不安から株価が下がっているのであれば、たとえ目先の配当利回りが魅力的な水準であっても、経営難を理由として将来的に配当を減らすこともありえます。
また、配当が増えている場合でも、利益を企業の成長に向けた投資に充てず、必要以上に配当に回しているケースも考えられます。企業の成長が停滞すれば、たとえ配当利回りが高くても、株価の値下がりによって利益が相殺されてしまうこともありえます。
高配当株への投資に当たっては、配当利回りだけでなく企業の業績や財務状況、成長性なども確認する必要があります。
高配当株は、ETFや投資信託でも投資できる
高配当株投資のメリットを享受するには、適切な銘柄を選ぶことが重要です。自分自身で銘柄選びをできれば良いのですが、日頃忙しくて情報収集のための時間が取れない、経験や知識がないために銘柄を選ぶのが難しいというのが、多くの個人投資家にとっての本音ではないでしょうか。そんな時に便利なのが投資信託やETFです(これらを総称して「ファンド」と呼びます)。
ファンドを使って高配当株に投資するメリット
高配当株を対象としたファンドを活用すれば、1つの商品で、しかも比較的少額で複数の銘柄に投資できます。個別銘柄への投資では銘柄選びに失敗すると大きな損失を被る可能性がありますが、ファンドであれば、たとえ投資先の1社が破綻しても、そのほかの銘柄で損失をカバーできる可能性があります。
また、ファンドには組み入れ銘柄を入れ替える機能や、組み入れ銘柄の比率を調整する「リバランス」の機能が備わっています。これまで高い配当を出し続けていた銘柄であっても、業績の悪化などにより減配あるいは無配になることや、逆に新たな高配当銘柄が台頭することがあります。組み入れ銘柄を定期的に見直すことで、ファンド全体の収益性が保たれています。さらに、リバランスにより「株価が上がった銘柄を売り、株価が下がった銘柄を買う」という調整を行うことで、特定の銘柄による影響が大きくならないようにしています。
個人投資家が個別銘柄の運用で銘柄の入れ替えやリバランスを行うのは、非常に手間がかかります。個別銘柄を売買する際には売買手数料も発生します。そしてNISA口座であれば年内の非課税投資枠が消費されるうえ、売却により損失が確定した場合は、課税口座との損益通算ができないというデメリットがあります。また、NISA口座以外では売却益は課税対象となります。
ファンドであれば、銘柄の入れ替えやリバランスに伴うこれらのコストは、運用中の手数料として投資家が間接的に支払うことになるものの、個別銘柄の運用と比較すれば小さく、ファンドで高配当株を運用するメリットとなります。
ただし、ファンドへの投資では、個別銘柄投資と違って株主優待を受け取ることはできません。また、短期間で大きな値上がり益を得られる可能性も個別銘柄ならではです。投資対象が分散され、リバランス機能を備えたファンドは、個別銘柄と比べると一般的に値動きは穏やかになります。
高配当株投資における個別銘柄とファンドのメリットとデメリット
| 個別銘柄 | ファンド(投資信託・ETF) | |
|---|---|---|
| メリット | ・配当だけでなく、株価が成長すれば短期的に大きな値上がり益も期待できる ・保有中の手数料がかからない |
・1本で、比較的少額で複数の銘柄に分散投資ができる ・銘柄選択の手間がかからない ・自動で銘柄入れ替えと組み入れ比率のリバランスが行われる |
| デメリット | ・銘柄選択のための情報収集に時間と手間がかかる ・最低投資金額がファンドより大きいことが多い ・売買時に手数料や課税が発生 ・投資先企業が破綻した場合の損失が大きい |
・保有中に手数料(信託報酬など)がかかる ・株主優待をもらえない ・短期的に大きな値上がりは期待しにくい |
投資信託とETFの違いは?
非上場の投資信託とETFの違いは、ETFは販売会社に支払う費用がなく信託報酬が低い傾向があること、個別銘柄と同じように変動する価格を見ながらリアルタイムで取引できることが挙げられます。投資信託はリアルタイムの取引こそできませんが、自動で積立投資をできるサービスや、分配金を自動で再投資できるサービスを利用できることがメリットです。
投資信託もETFも分配金が支払われることは共通ですが、ETFの分配金は株式の配当のみを原資とするのに対し、投資信託は「特別分配金(元本払戻金)」と呼ばれる、元本から払い出す形の分配金もありえます。分配金を再投資せずに受け取る場合、元本払戻金により個別元本が減少すると、その後の基準価額の上昇による恩恵を十分に得られなくなることがあります。
高配当株投資における投資信託とETFのメリットとデメリット
| 非上場の投資信託 | ETF | |
|---|---|---|
| メリット | ・金融機関によっては100円から購入が可能 ・積立投資や分配金再投資のサービスが利用できる |
・変動する価格を見ながらリアルタイムで取引できる ・信託報酬が投資信託より低い傾向 |
| デメリット | ・信託報酬がETFより高い傾向 ・元本払戻金により個別元本が減少し、複利効果が薄れる可能性 |
・一部の証券会社を除いて、自動で積立投資ができない ・分配金再投資をする場合、その都度購入手続きが必要 |
高配当株ETFが連動を目指すさまざまな株価指数
国内株式を対象とする高配当株ETFは、高配当株指数への連動を目指す「インデックス型」と、銘柄選択によって市場平均を上回る成果を目指す「アクティブ型」の2種類に大きく分けられます。一般に、信託報酬はアクティブ型の方が、インデックス型と比べて高い傾向があります。
インデックス型のETFが連動を目指す指数の種類もさまざまです。投資対象のユニバース(母集団)や銘柄選定のフロー、銘柄数、リバランスの頻度などが異なる高配当株指数が複数あり、それぞれの指数を対象とするETFが東証に上場しています。ETFを選ぶ際には、これらの指数の特徴を比較することが大切です。
高配当株指数の注目ポイント
- ユニバース……時価総額上位銘柄、日経平均株価の225社、東証上場全銘柄など
- 銘柄選定フロー……予想配当利回り、流動性、財務体質など選定の際に重視する項目
- 銘柄構成ウェイト……時価総額加重、均等加重など
- リバランス……年1回、年2回、年4回など
- 銘柄数
- 指数全体での配当利回り
指数の注目ポイントを「ブルームバーグ日本株高配当50指数」で確認
「ブルームバーグ日本株高配当50指数」は、国内株式市場の高配当株を対象とした株価指数のひとつです。下図のように、他の主要な高配当株指数と比較してリバランスの回数が多いことと、配当利回りの予想に「ブルームバーグ配当予想」を利用することが主な特徴です。ブルームバーグ配当予想は、複数のアナリストによる最新の予想をいち早く取り込むことが、企業が発表する予想配当金をもとに算出する一般的な予想配当利回りと異なる点です。
ブルームバーグ日本株高配当50指数の特徴
| 特徴 | 他の指数との違い | |
|---|---|---|
| ユニバース | 東証上場株式のうち、時価総額上位500銘柄 | TOPIX100構成銘柄や、日経平均株価構成銘柄をユニバースとする指数もある |
| 銘柄選定フロー | 直近90日間の平均売買代金上位400銘柄かつ、予想配当利回りデータの提供元が3社以上の銘柄を選出。さらに当期損益で利益を計上している銘柄で、予想配当利回り(ブルームバーグ)の上位から以下の優先度で選定 ①25位以内 ②採用済みで75位以内 ③50に満たない場合、残りの上位から採用 |
予想配当利回りを対象とする指数と、直近の実績配当利回りを対象とする指数がある。当指数では、予想配当利回りの算出に複数のアナリストによる予測を用いるのが特徴。このほか、財務体質を重視する指数もある |
| 銘柄構成ウェイト | 均等加重 | 時価総額加重の指数では株価の上昇率が高い銘柄の比率が高まりやすいのに対して、均等加重の指数では上昇率が高い銘柄ほどリバランスの際に売られ、相対的に株価が安い銘柄は買われることになるため、指数自体が「高く売って安く買う」という性質を持つ |
| リバランス | 年4回 | 他の主要指数は年1回・年2回。リバランスの回数は比較的多い |
| 銘柄数 | 50 | 他指数では30~70程度 |
高配当株ETFにはどんな銘柄がある?
国内の高配当株を投資対象とするETFには、TOPIX100指数の構成銘柄をユニバースとする「TOPIX高配当40指数」への連動を目指すものがあるほか、先ほど紹介した「ブルームバーグ日本株高配当50指数」への連動を目指す銘柄が2025年4月17日に上場しました。
まとめ
高配当株は、株式投資における人気テーマのひとつです。高配当株投資は個別銘柄への投資だけでなく、投資信託やETFを活用して投資する方法もあります。特にETFは比較的少額から複数の高配当株に分散投資でき、投資金額を徐々に積み上げていくことで受け取る配当を増やしていくこともできます。ETFは株式と同様にリアルタイムで取引可能なうえ、信託報酬も投資信託と比較して低い傾向があることがメリットです。
高配当株投資で注意すべきことは、必ずしも「高配当=高収益」とは限らないということです。たとえ配当が多くても、株価が下がってしまえば損益はマイナスになりかねません。個別銘柄への投資はリスクが大きいため、特に投資初心者の方は、ETFなどを活用するのが現実的な手段といえるでしょう。
高配当株指数への連動を目指すインデックス型のETFにはさまざまな種類があります。指数ごとに銘柄構成ウェイトや銘柄選定フローなどが異なるため、組み入れられる株式やその配分はETFごとに異なり、得られる収益も変わってきます。ETFを選ぶ際には、それぞれの指数の特徴を知ることが大切です。